突然の激しい動悸、息苦しさ、胸の痛み、めまい、そして「死んでしまうのではないか」という強い恐怖感…。こうした症状を繰り返し経験する「パニック障害」は、日常生活に大きな影響を与える心の病のひとつです。多くの人が「強いストレスが原因では?」と考えがちですが、実はストレス以外にもさまざまな“引き金”が関係していることが分かっています。
今回は、パニック障害の基本的な種類やきっかけ、意外な引き金、対処法、そして予防のヒントまで、やさしく丁寧にデジりすさんと解説していきます。
デジりすさんってだあれ?(ココをタップ♬)

デジキャリIT就労移行支援事業所のキャラクターであり、Instagramでは様々な知識を教えているよ!
パニック障害とは?

パニック障害とは、特別な理由がないにもかかわらず、突然パニック発作が起こり、それが繰り返される状態を指します。発作には、心拍数の増加、過呼吸、胸の痛み、吐き気、めまい、冷や汗、体の震えなどが含まれ、発作が起きた場面に対して強い不安を感じるようになり、外出や人混みを避けるようになることもあります。
以前は「心の弱い人がなる病気」と誤解されがちでしたが、近年は脳の神経伝達物質や自律神経の働きが関係していることが分かってきました。
パニック障害の種類
パニック障害にはいくつかの側面があります。
- パニック発作:突然、激しい不安や恐怖を感じる発作。数分から30分ほどでおさまるが、非常につらい。
- 予期不安:次にいつ発作が来るか分からないという不安に常におびえている状態。
- 広場恐怖:発作が起きたときに逃げられない・助けを得られないと思われる場所を避ける傾向。
これらが重なり合って、日常生活に支障が出ることも少なくありません。
よくあるきっかけや原因
パニック障害が発症する背景には、次のような要因があります。
- 強い心理的ストレス(仕事・家庭・人間関係など)
- トラウマ的な体験(事故・災害・病気など)
- 不安になりやすい性格(几帳面、まじめ、責任感が強い)
- 睡眠不足や過労
- カフェインやアルコールの過剰摂取
- 自律神経の乱れ
これらが重なったり、継続的に蓄積されたりすると、ある日突然パニック発作として表面化することがあります。
意外な引き金とは?
パニック障害を引き起こすきっかけはストレスだけではありません。以下のような、意外と見過ごされがちな要素が関与していることもあります。
1. カフェインの取りすぎ
コーヒー、エナジードリンク、紅茶などに含まれるカフェインは、交感神経を刺激し、心拍数を上げたり不安感を高めたりすることがあります。敏感な人にとっては発作の引き金になりうるのです。
2. 月経やホルモンバランスの変化
女性の場合、PMS(月経前症候群)や更年期に関連するホルモンの変動が、心のバランスにも影響を与え、発作を誘発することがあります。
3. 首や肩のこり
身体の緊張状態が続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなります。とくに首や肩まわりのこりが強いと、めまいや息苦しさを感じやすくなり、不安と結びつくことがあります。
4. 天候や気圧の変化
気圧の変動が激しい日は、自律神経の働きが乱れやすく、不調を感じやすくなる人が増えます。これが不安感やパニック発作を引き起こすことも。
5. 過去の体験との結びつき
以前にパニック発作が起きた場所や状況に似た場面に遭遇すると、無意識のうちに身体が反応して発作が再現されることがあります。

カフェインの摂りすぎで、なることもあるんだ!
対処法:発作が起きたときどうする?

発作が起きてしまったときは、まず「これは病気の症状であり、必ずおさまる」と理解することが大切です。
- 安全な場所に座る、横になる
- ゆっくりと深呼吸する(4秒吸って、6秒吐く)
- 身体の感覚に意識を向ける(手を握る、足を地面につけるなど)
- 誰かに連絡をとる(話すことで安心できる)
無理に落ち着こうとするより、「波が過ぎるのを待つ」ような感覚でいると、症状が和らぎやすくなります。
予防のためにできること
パニック障害を予防・緩和するためには、日頃の生活習慣や考え方の見直しも重要です。
1. 規則正しい生活を心がける
睡眠・食事・運動のリズムを整えることで、自律神経が安定しやすくなります。
2. 情報との距離をとる
不安になりやすい人は、ニュースやSNSから受ける刺激にも影響されがちです。必要以上に情報を取りすぎない工夫も大切です。
3. カフェイン・アルコールを控える
体調が不安定なときほど、刺激物は少なめに。飲み物をノンカフェインにするなどの工夫も有効です。
4. リラクゼーションを取り入れる
深呼吸、ストレッチ、瞑想、アロマテラピーなど、自分が「ほっとする」時間を意識的につくってみましょう。
5. 心のモヤモヤを書き出す
ジャーナリングや日記で、不安や緊張を外に出すだけでも、気持ちが整理されることがあります。
6. 専門家に相談する
発作が続くようであれば、精神科や心療内科を受診することも大切です。治療には薬物療法や認知行動療法が用いられます。

できることから実践しよう
おわりに
パニック障害は、決して「心が弱い人の問題」ではありません。誰でも、生活や環境の変化、体調の変化、あるいは思いがけない引き金で発症する可能性があります。
「ストレスだけじゃない」
それを知るだけでも、自分を責める気持ちは少し軽くなるのではないでしょうか。
大切なのは、「これは病気なんだ」と受け止め、自分の体と心にやさしく向き合っていくこと。発作があっても安心して暮らしていけるよう、少しずつできることから取り入れてみてください。
必要なときは、誰かの手を借りてもいいのです。
デジりすさんからのアドバイス
「チェックリストを活用しながら考えてみよう
断ることはダメなことじゃないよ」

今回はトライアル雇用のミスマッチについてお伝えしてきました。トライアル雇用は求職者と企業が相互に適性を確認するための制度ですが、実際に働いてみるとミスマッチを感じることもあります。ミスマッチを感じたら、まずは冷静に自己分析し、対応策を考えることが大切です。話し合いで解決できる場合もあるため、まずは相談し、それでも難しい場合は丁寧に申し出るようにしましょう。
私たちデジキャリIT就労移行支援事業所では、障害等の事情があって就職・再就職に悩んでいる方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

見学・体験へのお申込み・相談は ☆
電話
・電話 092-406-3367 (電話受付時間 平日9時30分~18時半)
・メール:support@degi-ca.com
からもお気軽にご相談くださいませ🐨
HP:https://degi-ca.com/
メール(件名にブログ経由で問合せと入れていただくと、問い合わせがスムーズです)
support@degi-ca.com
(件名にブログ経由で問合せと入れていただくと、問い合わせがスムーズです)
ホームページ
https://degi-ca.com/
からもお気軽にご相談くださいませ🐨
メールでのご相談は、下記項目から可能な範囲で共有いただけますと幸いです。
(1)お名前
(2)性別
(3)お住まい(住所)
(4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可)
(5)診断名(任意)
(6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると幸いです)
(7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)
#Webデザイン #動画編集 #htmlcss #就活 #うつ病 #発達障害 #適応障害 #hsp #就労移行支援 #デジキャリIT #障害者雇用
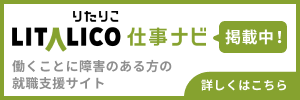



うつ病から抜け出す!立ち直るきっかけは?社会復帰への方法-620x360.jpg)



障害者の法定雇用率とは-160x160.jpg)




