「人前に出るのが怖い」「何か話そうとすると、頭が真っ白になる」「嫌われたらどうしようって、ずっと考えてしまう」。そんな思いを抱えながら、学校や仕事、日常生活をがんばっている方がいます。
このような不安は、誰にでも多少はあるものです。でも、その不安が強すぎて、日常生活に大きな支障が出ている場合は、「社会不安障害(社交不安障害)」と呼ばれる心の不調かもしれません。
この記事では、社会不安障害の特徴や原因、症状、対処法までを、デジりすさんとやさしく丁寧にお伝えしていきます。
「もしかして自分もそうかも」と感じている方や、大切な誰かが不安に悩んでいる方にとって、少しでも安心のヒントになるような時間となりますように。
デジりすさんってだあれ?(ココをタップ♬)

デジキャリIT就労移行支援事業所のキャラクターであり、Instagramでは様々な知識を教えているよ!
社会不安障害の主な特徴

社会不安障害とは、「人からどう思われているか」が強く気になってしまい、人前に出ることや他者との交流に強い恐怖を感じる状態です。ただの「恥ずかしがり」や「人見知り」とは違い、その不安がとても強く、日常生活を困難にすることが特徴です。
たとえば、こんなことに強い不安を感じます__
- 人前で話す、発表する
- 注目される
- 上司や先生に報告・相談する
- 食事を人前でとる
- 電話をかける・受ける
- まわりから「変だと思われたらどうしよう」と感じる
不安が高まると、顔が赤くなる、声が震える、動悸がするなど、身体にもさまざまな反応が現れることがあります。
それが「また同じことが起きたらどうしよう…」という思いにつながり、人を避けたり、行動自体をやめてしまうことも少なくありません。
ただの緊張とどう違うの?
「人前に立つときに緊張するのは、誰だってそう」と言われることがあります。たしかに、人と関わるときに多少の不安や緊張を感じるのは自然なことです。
でも、社会不安障害の方の不安は、以下のような特徴があります__
- 小さなことでも過剰に反応してしまう
- 不安や恐怖の強さが、日常生活に大きく影響している
- 「避ける」ことで生活の幅がどんどん狭くなってしまう
- 頭では「考えすぎかも」と思っても、気持ちがついてこない
たとえば、「注文のときに噛んだらどうしよう」と考えて、飲食店に入ること自体を避けたり、電話対応が怖くて仕事を辞めてしまったり。「ただの緊張」とは違い、不安の強さが生活を制限し、本人にとってはとてもつらい状況なのです。

不安が大きいと負担が大きいよね
社会不安障害の原因と背景

社会不安障害の原因は、一つだけではありません。いくつかの要素が重なり合って起こると考えられています。
■ 性格の傾向
- 真面目で責任感が強い
- 周囲の目を気にする
- 失敗を過剰に恐れてしまう
- 完璧主義である
このような傾向は、決して悪いことではありません。でも、ちょっとしたミスや指摘を「自分がダメだから」と強く責めてしまうことで、不安のサイクルが強まっていくことがあります。
■ 過去の体験
- 子ども時代にいじめや否定的な体験をした
- 人前で失敗し、強く恥をかいた記憶がある
- 家庭や学校などで人間関係にトラブルがあった
こうした体験が「また同じようなことが起きるかも」という恐怖につながることもあります。特に、感受性の強い人ほど、過去の経験が心に残りやすい傾向があります。
■ 脳の働き・遺伝的な影響
社会不安障害の背景には、脳内の神経伝達物質(セロトニンなど)のバランスが影響しているとも言われています。
また、家族に同じような不安傾向がある場合、遺伝的な要素が関係している可能性もあると考えられています。
どんな症状が出る?心と体のサイン
社会不安障害では、心だけでなく、体にもさまざまな症状が現れます。しかもその症状は、本人にとって「コントロールできない」と感じるほど強く、日常生活に大きな影響を与えることがあります。
■ 体に出るサイン
- 動悸や息苦しさ
人前に出る直前や注目されたときに、胸がドキドキして呼吸が浅くなることがあります。 - 手の震え・声の震え
緊張のあまり、マイクを持つ手が震えたり、声がうまく出なかったりすることがあります。 - 顔が赤くなる・汗をかく
「見られている」と感じると、急に顔が火照ったり、手に汗をかいてしまうことも。 - めまい・吐き気・頭痛
極度の不安で、ふらついたり、胃の不調を感じたりする方もいます。
これらは「気のせい」ではなく、自律神経が乱れることで実際に起こる生理的反応です。症状そのものがさらに「恥ずかしい」と感じることで、不安が悪化する…という悪循環に陥ることもあります。
■ 心に出るサイン
- 「変に思われたらどうしよう」という思考
自分の言動が相手にどう思われるかを過剰に気にしてしまい、行動そのものが怖くなります。 - 過去の場面を何度も思い出して落ち込む
うまく話せなかったことを繰り返し思い出し、「また同じことが起きたらどうしよう」と未来を不安視してしまいます。 - 自分を責める思考が強くなる
「自分はダメだ」「こんなこともできないなんて」といった自己否定が続き、自己肯定感が下がっていきます。 - 回避行動が増える
怖い場面を避けようとするうちに、人との関わりそのものが減り、孤立を深めてしまうこともあります。
これらの心と体のサインは、どれも「甘え」ではありません。真面目でがんばり屋さんほど、自分のつらさを軽視してしまいがちですが、「つらい」と感じることそのものが、すでに十分なサインなのです。
対処法とサポートの選び方

社会不安障害に対しては、さまざまなサポートや対処法があります。「怖い気持ちがあること」を前提にしながら、自分のペースで安心を増やしていくことが大切です。
■ 自分でできるセルフケア
- 呼吸をゆっくり整える
緊張を感じたときは、呼吸が浅くなりがちです。吸うよりも「ゆっくり吐く」ことを意識するだけでも、体の反応は少しずつ落ち着いていきます。 - 小さな成功体験を積む
不安の大きい場面に無理して飛び込むよりも、少し不安を感じるくらいの「できそうなこと」から始めましょう。
たとえば「挨拶だけする」「短い一言だけ発表してみる」など。 - 失敗を「ダメなこと」と思わない練習
うまくいかなかったときも、「練習の一歩だった」と受け止めることができれば、不安を乗り越える力が少しずつ育ちます。 - 考えすぎてしまうときは、手を動かす
不安な考えがぐるぐるしてしまうときは、掃除や手芸、日記を書くなど、手を使う作業をするのも効果的です。思考が少し整理されやすくなります。
■ 専門的なサポートを受ける
- カウンセリング(心理療法)
認知行動療法(CBT)は、社会不安障害の治療において効果が実証されています。
「不安を感じる思考のクセ」や「回避行動」への向き合い方を、専門家と一緒に練習していく方法です。 - お薬によるサポート
必要に応じて、不安を和らげるお薬(抗不安薬、抗うつ薬など)が処方されることもあります。
「薬=依存」と心配される方もいますが、正しく使えば回復の一助になる大切な選択肢のひとつです。 - 医療機関・支援機関の利用
心療内科や精神科だけでなく、就労支援施設やカウンセリングルームでも相談ができます。
「診断が出るのが怖い」という声もありますが、「ラクになるためのヒントをもらう場所」と考えてみてもよいかもしれません。
■ 周囲の理解を得る工夫
- 無理に「わかってもらおう」としなくてもいい
すべての人に自分の不安を理解してもらう必要はありません。信頼できる少人数とだけ、少しずつ話していくことでも十分です。 - 言葉で伝えづらいときはメモやLINEでもOK
気持ちを伝える手段は、話すことだけではありません。文章にして伝えることで、自分の気持ちが整理されることもあります。

周りの力を借りよう!
ゆっくり、自分らしく過ごすために
社会不安障害は、誰かに見られていると感じる場面や、人と関わる状況で、強い不安や緊張が生まれてしまう心の病気です。
けれど、それは「性格のせい」でも「努力が足りないせい」でもありません。むしろ、丁寧で真面目な気質を持つ方が、自分の思いや行動を強く意識しすぎてしまうことが背景にあることも多いのです。
「こんな自分はおかしいのでは」と感じる瞬間があっても、その不安の奥には、人とうまくやりたい、迷惑をかけたくないという優しさがあるはずです。
大切なのは、つらさを一人で抱えこまず、少しずつ安心できる場所や方法を増やしていくことです。社会不安障害は、早めに気づいて対処を始めることで、ゆっくりでも確実に「安心できる時間」を取り戻していくことができます。
どんなに小さな一歩でも、それはたしかに「自分らしく生きる道」の上にあります。
どうか、自分にやさしくいられる時間を、少しずつ増やしていけますように。
デジりすさんからのアドバイス
「不安に思っている自分を受け入れ
周りのサポートやセルフケアで対処していこう」

今回は社会不安障害についてお伝えしてきました。社会不安障害という言葉を初めて知った方も、もしかして自分もそうかもしれない…と感じた方も。このページにたどりついてくださったということは、きっとどこかに「今の自分を理解したい」「少しでもラクになりたい」という気持ちがあったのだと思います。
不安は、無理やり追い払おうとしなくても大丈夫です。まずは、「不安がある自分」を責めずに受けとめること。そして、できるところから少しずつ、自分のためのやさしい工夫やサポートを取り入れていけたら、それだけでも、あなたの毎日はきっと変わっていきます。
私たちデジキャリIT就労移行支援事業所では、障害等の事情があって就職・再就職に悩んでいる方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

見学・体験へのお申込み・相談は ☆
電話
・電話 092-406-3367 (電話受付時間 平日9時30分~18時半)
・メール:support@degi-ca.com
からもお気軽にご相談くださいませ🐨
HP:https://degi-ca.com/
メール(件名にブログ経由で問合せと入れていただくと、問い合わせがスムーズです)
support@degi-ca.com
(件名にブログ経由で問合せと入れていただくと、問い合わせがスムーズです)
ホームページ
https://degi-ca.com/
からもお気軽にご相談くださいませ🐨
メールでのご相談は、下記項目から可能な範囲で共有いただけますと幸いです。
(1)お名前
(2)性別
(3)お住まい(住所)
(4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可)
(5)診断名(任意)
(6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると幸いです)
(7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)
#Webデザイン #動画編集 #htmlcss #就活 #うつ病 #発達障害 #適応障害 #hsp #就労移行支援 #デジキャリIT #障害者雇用
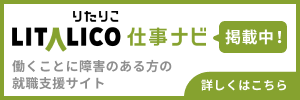







障害者の法定雇用率とは-160x160.jpg)




