「最近、ちょっと怒りっぽくなった気がする」「なんであんなことを言ってしまったのか自分でもわからない」
事故や病気をきっかけに、以前とは違う自分に戸惑う方や、そのご家族の困りごととして多いのが「感情のコントロールのしづらさ」です。
これは、脳の損傷によって起こる“高次脳機能障害”の一症状であり、ときに「社会的行動障害」と呼ばれることもあります。
しかし、こうした症状は見た目ではわかりにくく、周囲からは「性格が変わった」「わざとやっているのでは」と誤解されがちです。今回は、この「感情コントロールの難しさ」に焦点をあて、高次脳機能障害についてやさしくデジりすさんと解説します。
デジりすさんってだあれ?(ココをタップ♬)

デジキャリIT就労移行支援事業所のキャラクターであり、Instagramでは様々な知識を教えているよ!
高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害とは、事故や病気などで脳が損傷を受けた後に生じる、記憶や注意、感情などの“目に見えにくい”障害のことです。
原因として多いのは、以下のようなものです。
- 脳外傷(交通事故や転倒による頭部打撲など)
- 脳卒中(脳出血・脳梗塞など)
- 脳炎、低酸素脳症 など
身体的な後遺症が目立たない場合でも、脳の中枢が傷つくことで、生活の中にさまざまな“困りごと”が現れます。
社会的行動障害とは?
社会的行動障害とは、特に感情や行動のコントロールに関わる機能に障害が出たときに見られる状態を指します。代表的な症状は以下のとおりです。
- 怒りっぽい・すぐカッとなる
- 思ったことをすぐ口に出す(抑制がきかない)
- 落ち着きがない・我慢ができない
- 他人の気持ちに配慮できないように見える
本人に悪気があるわけではなく、脳の損傷によって“ブレーキをかける力”が弱くなっているために起こる症状です。
感情コントロールと脳の働き
感情をコントロールする機能は、主に「前頭葉」と呼ばれる脳の部分で担われています。この領域が損傷すると、次のような困難が生じることがあります。
- 衝動を抑えられない
- 状況に応じた行動の選択が難しくなる
- 相手の気持ちや社会的なルールを考える力が弱まる
特に「前頭前野」と呼ばれる部分が関係しており、ここは“理性”や“判断”をつかさどる非常に重要なエリアです。事故や脳卒中でこの部分にダメージがあると、感情が爆発しやすくなったり、社会的なふるまいにズレが生じたりするのです。

感情のコントロールも難しくなるんだね
よくある誤解と支援者・家族の戸惑い

高次脳機能障害の「社会的行動障害」は、パッと見て分かりにくいため、以下のような誤解が生まれやすくなります。
- 「大人なのに、子どもみたいに我慢できない」
- 「以前はこんな人じゃなかったのに」
- 「わざと怒っているのでは?」
家族や支援者も、最初は戸惑い、疲れ果ててしまうこともあります。変わってしまった相手をどう受け止めたらいいのか分からず、孤立感や無力感にさいなまれることも少なくありません。
しかし、「本人も困っている」という視点を持つことで、少しずつ関係が変わっていくことがあります。
本人が抱えるつらさ

感情がコントロールできないという状態は、本人にとっても非常に苦しいものです。
- 「どうしてもイライラが止まらない」
- 「また怒ってしまった…と自己嫌悪になる」
- 「人間関係がうまくいかなくて落ち込む」
“自分でもコントロールできない感情”が続くことで、うつ状態や引きこもりにつながってしまうケースもあります。外からは「わがまま」に見える行動の裏に、深い苦悩や自責の念が隠れているのです。
だからこそ、本人を責めるのではなく、「困りごとの背景には脳の損傷がある」という理解が必要なのです。
周囲にできること
高次脳機能障害のある方と接するうえで、周囲にできることはたくさんあります。
1. 感情的に反応しすぎない
突然怒り出したり、大きな声を出されたりすると、ついこちらも動揺してしまいますが、可能な限り冷静に対応することが大切です。
2. 状況を整える
ストレスの多い環境では症状が悪化することも。静かな場所を選んだり、予定を詰めすぎないよう配慮することで、落ち着いて過ごせる場をつくることができます。
3. 支援者や医療機関と連携する
医師、作業療法士、相談支援専門員、リハビリ関係者などの専門職と連携することで、よりよい対応方法や環境整備のアドバイスが得られます。
4. 本人の「できたこと」に注目する
できないことや困った行動ばかりが目につきやすくなりますが、小さな成功体験を一緒に喜ぶことが、回復への力になります。

一緒に整理してあげることが大切だよ
利用できる支援制度・相談先

高次脳機能障害に関連する支援は、医療・福祉・就労・教育など多岐にわたります。
- 地域の障害者相談支援事業所:生活面での困りごとに関する相談ができます。
- 自立支援医療制度:医療費の自己負担軽減に役立ちます。
- 就労移行支援・就労継続支援:働く準備や職場定着の支援を行ってくれます。
- 高次脳機能障害支援拠点病院や支援センター:地域によっては専門の相談窓口があります。
必要に応じて、障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の取得も検討されます。公的なサポートを活用することで、生活の負担が軽減されることがあります。
地域社会での理解を広げるために
高次脳機能障害、とくに社会的行動障害については、まだまだ社会的な認知が十分とは言えません。
地域での講演会や本人・家族の語り、学校での福祉教育などを通じて「見えにくい障害」への理解を深めていくことが大切です。
また、職場や学校においても、以下のような取り組みが役立ちます。
- 感情の起伏がある人への対応マニュアルの作成
- 定期的な面談やストレスチェック
- ピアサポーターの配置や相談窓口の整備
一人ひとりが「見えない障害があるかもしれない」と意識するだけで、より安心して暮らせる社会につながります。
デジりすさんのひとこと
「見えないつらさにも、ちゃんと理由がある
まずは知ることから始めよう」

今回は高次脳機能障害の社会的行動障害についてお伝えしてきました。高次脳機能障害による感情のコントロールのしづらさ、それは本人の「努力不足」ではありません。脳の損傷という“目に見えにくい”要因によって起こる、れっきとした障害の一つです。
「性格の問題」と片づけるのではなく、「どうすれば本人が安心して暮らせるか」という視点を持つことが、真の支援につながります。
私たち一人ひとりの理解と、小さな気づきが、誰かの心の支えになるかもしれません。
私たちデジキャリIT就労移行支援事業所では、障害等の事情があって就職・再就職に悩んでいる方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

見学・体験へのお申込み・相談は ☆
電話
・電話 092-406-3367 (電話受付時間 平日9時30分~18時半)
・メール:support@degi-ca.com
からもお気軽にご相談くださいませ🐨
HP:https://degi-ca.com/
メール(件名にブログ経由で問合せと入れていただくと、問い合わせがスムーズです)
support@degi-ca.com
(件名にブログ経由で問合せと入れていただくと、問い合わせがスムーズです)
ホームページ
https://degi-ca.com/
からもお気軽にご相談くださいませ🐨
メールでのご相談は、下記項目から可能な範囲で共有いただけますと幸いです。
(1)お名前
(2)性別
(3)お住まい(住所)
(4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可)
(5)診断名(任意)
(6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると幸いです)
(7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)
#Webデザイン #動画編集 #htmlcss #就活 #うつ病 #発達障害 #適応障害 #hsp #就労移行支援 #デジキャリIT #障害者雇用
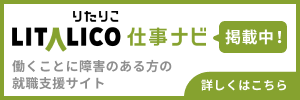







障害者の法定雇用率とは-160x160.jpg)




