「なんとなくいつも不安」
「人と会うたび緊張して疲れる」
「失敗が怖くて行動できない
そんな気持ちに、心当たりはありませんか?
私たちは誰しも、不安や緊張を感じながら日常を生きています。しかし、その不安があまりに強く、生活に支障をきたしてしまうとしたら。それは「不安障害」と呼ばれる心の状態かもしれません。
この記事では、「不安障害ってどんなもの?」という疑問に丁寧に寄り添いながら、主な種類や症状、見分け方、そして日常生活でできるケアの方法までデジりすさんとご紹介します。
デジりすさんってだあれ?(ココをタップ♬)

デジキャリIT就労移行支援事業所のキャラクターであり、Instagramでは様々な知識を教えているよ!
不安って誰にでもあるもの?

不安とは、未来に起こるかもしれない出来事に対して抱く、警戒心のような感情です。試験の前や新しい場所に行くとき、誰でも多少の不安は感じるもの。それ自体は自然で、生きていく上で大切な感情でもあります。
しかし、その不安が「理由もないのに毎日続く」「些細なことが気になって仕方がない」「体調にも影響が出る」など、日常に影響を与えてしまうようになると、不安障害の可能性が出てきます。
不安障害とは?
不安障害(anxiety disorders)は、強すぎる不安や恐怖を感じ、それによって日常生活に支障をきたしてしまう精神的な疾患の総称です。本人にとっては「心配しすぎ」と言われても抑えられないほど、心が常に警戒状態にあります。
不安障害は「性格の問題」や「気の持ちよう」ではなく、れっきとした心の病気です。治療や支援によって回復を目指すことができます。
不安障害の種類と特徴

不安障害にはいくつかのタイプがあり、それぞれに異なる特徴があります。以下は代表的なものです。
全般性不安障害(GAD)
特徴:日常生活のあらゆることに対して、過剰な不安や心配が長期間続く
例:仕事・健康・家族・お金など、常に「悪いことが起きるのでは」と気にしてしまう
症状:集中力低下、疲れやすさ、筋肉のこわばり、胃腸の不調など
パニック障害
特徴:突然、強烈な不安と身体症状に襲われる発作(パニック発作)が繰り返される
症状:動悸、呼吸困難、めまい、発汗、死への恐怖など
発作後、「また起きたらどうしよう」という予期不安も大きな問題に
社交不安障害(社交不安症)
特徴:人前で話す・食事する・人と接するなどの場面で強い不安を感じる
症状:赤面、震え、吐き気、強い緊張、回避行動
「恥をかきたくない」「変に思われたらどうしよう」という気持ちが根底にある
強迫性障害(OCD)
特徴:不安を打ち消すために、特定の考えや行動(強迫)を繰り返してしまう
例:「手が汚れているのでは」と思い何度も手を洗う、「鍵を閉めたか不安で何度も確認する」など
PTSD(心的外傷後ストレス障害)
特徴:強い恐怖体験(事故、災害、暴力など)のあと、不安や恐怖がフラッシュバックする
症状:悪夢、過覚醒、回避行動、怒りっぽさなど

不安の中にも種類があるんだね
どこまでが「普通の不安」で、どこからが「不安障害」?

「これって病気なの?ただの心配性じゃないの?」と感じる方も多いと思います。
不安障害を疑うポイントは、「その不安が生活にどれだけ影響しているか」です。
【チェックポイント】
□不安や心配が6ヶ月以上続いている
□原因がはっきりしないのに不安になる
□身体にも不調が出ている(動悸・胃痛・頭痛など)
□日常生活や仕事、人間関係に支障が出ている
□不安を避けるために行動を制限している
これらに該当する場合、一度専門家に相談することをおすすめします。
不安障害の原因は?
不安障害の原因は1つではなく、いくつかの要素が重なって発症すると考えられています。
① 脳内物質のバランスの乱れ
セロトニンやノルアドレナリンといった神経伝達物質がうまく働かないことで、不安が強まりやすくなります。
② 生まれ持った性質(気質)
不安になりやすい気質(慎重、敏感、完璧主義)を持つ人は、発症のリスクが高いとされます。
③ 環境やストレス
いじめ、家庭環境の不安定さ、過労、離別などの強いストレスがきっかけになることもあります。
④ 過去の体験
過去に強い不安や恐怖を体験したことが、再び不安を引き起こすきっかけになることもあります。
不安障害の治療とセルフケア

専門的な治療法
薬物療法:抗不安薬や抗うつ薬を使用し、神経伝達物質のバランスを整える
認知行動療法(CBT):不安を引き起こす思考パターンを見直し、柔軟な考え方を学ぶ
日常生活でできるセルフケア
睡眠と食事を整える:規則正しい生活リズムが不安を和らげます
運動を取り入れる:軽い運動でも気分をリフレッシュしやすくなります
呼吸法・マインドフルネス:呼吸を整え、今ここに意識を向けることで過剰な不安を鎮めます
SNSやニュースとの付き合い方を見直す:不安を煽る情報は距離を取ることも必要
信頼できる人と話す:ひとりで抱え込まないことが大切です

規則正しい生活が第一歩!
「安心できる環境」を作ることから始めよう
不安障害と向き合ううえで大切なのは、「安心できる場所・人・習慣」を少しずつ整えていくことです。完璧に不安をなくそうとするのではなく、安心できる時間を増やす工夫をしていく。それが、少しずつ心の余裕を取り戻す第一歩になります。
また、「他人と比べない」「自分を責めすぎない」ことも忘れないでください。不安を感じやすい人ほど、自分を責めてしまう傾向にあります。そんなときこそ、「これでもよく頑張っている」と自分に優しい言葉をかけてあげましょう。
デジりすさんからのアドバイス
「安心できるモノやコトを見つけ
強い不安を感じたときに実践してみよう」

今回は不安障害についてお伝えしてきました。不安障害は、誰にでも起こりうる心の不調です。そして、決して珍しいことではありません。
「もしかして自分もそうかも」と感じた方へ。まずは、「そんな自分を否定しないこと」から始めてみてください。不安に悩むあなたは決して弱い人ではなく、むしろ真面目で繊細で、頑張り屋さんな人かもしれません。
ゆっくりと、自分の心と対話しながら、必要なサポートを受け取っていきましょう。不安と共に生きる道は、きっとあります。そしてその道の先には、今よりも少し穏やかな日々が待っているかもしれません。
私たちデジキャリIT就労移行支援事業所では、障害等の事情があって就職・再就職に悩んでいる方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

見学・体験へのお申込み・相談は ☆
電話
・電話 092-406-3367 (電話受付時間 平日9時30分~18時半)
・メール:support@degi-ca.com
からもお気軽にご相談くださいませ🐨
HP:https://degi-ca.com/
メール(件名にブログ経由で問合せと入れていただくと、問い合わせがスムーズです)
support@degi-ca.com
(件名にブログ経由で問合せと入れていただくと、問い合わせがスムーズです)
ホームページ
https://degi-ca.com/
からもお気軽にご相談くださいませ🐨
メールでのご相談は、下記項目から可能な範囲で共有いただけますと幸いです。
(1)お名前
(2)性別
(3)お住まい(住所)
(4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可)
(5)診断名(任意)
(6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると幸いです)
(7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)
#Webデザイン #動画編集 #htmlcss #就活 #うつ病 #発達障害 #適応障害 #hsp #就労移行支援 #デジキャリIT #障害者雇用
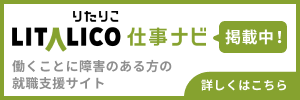







障害者の法定雇用率とは-160x160.jpg)




